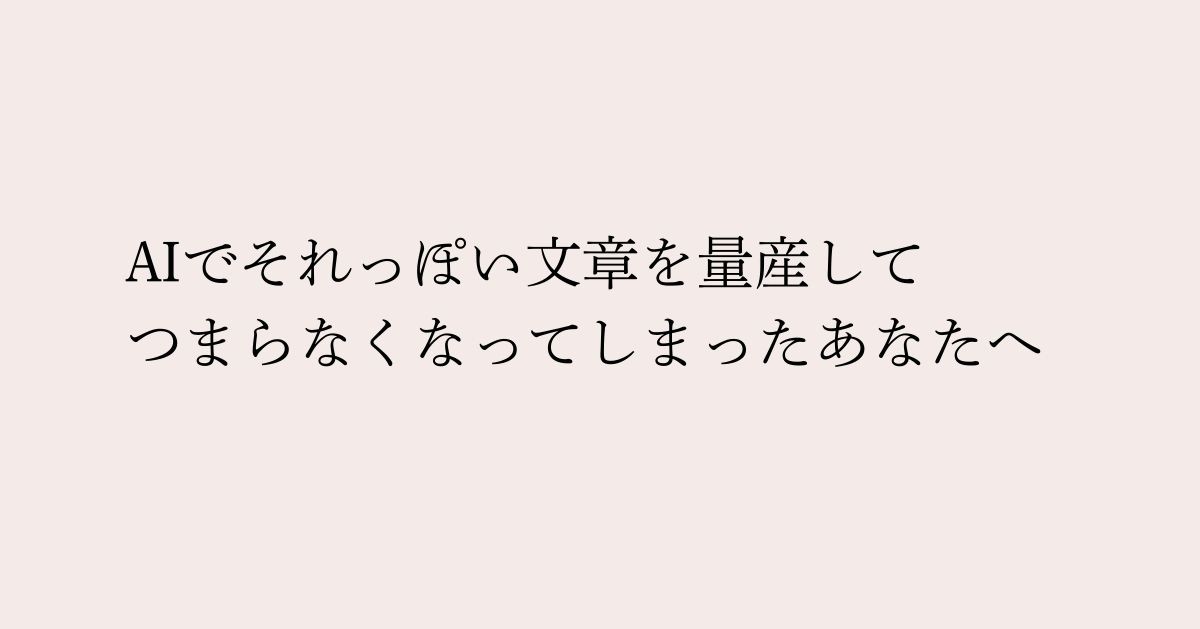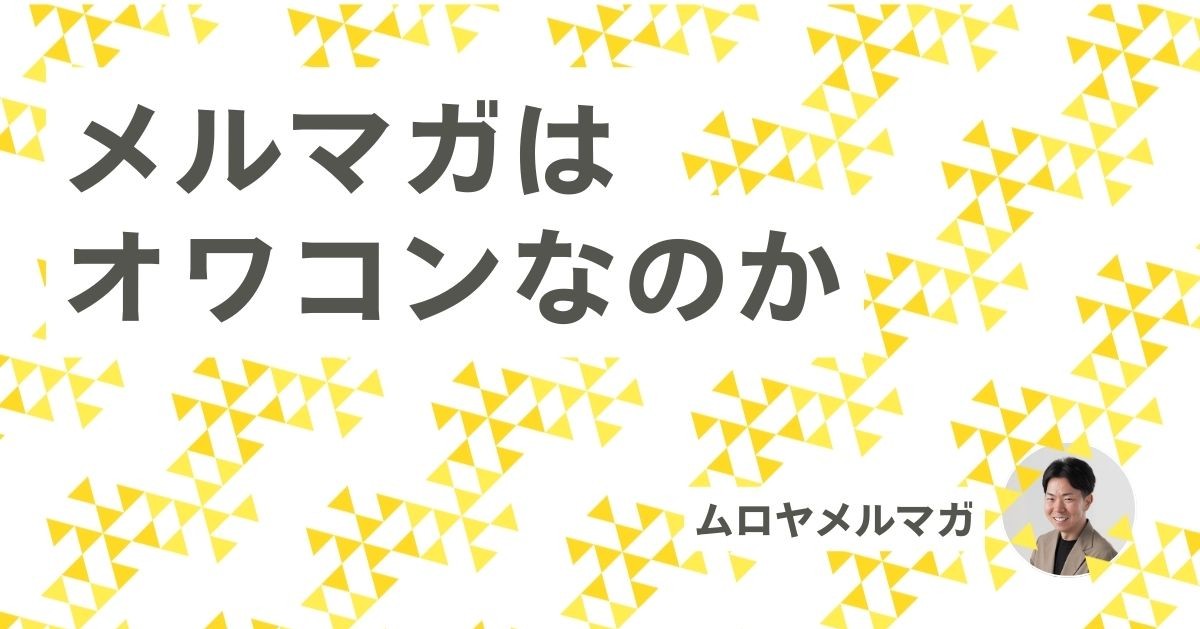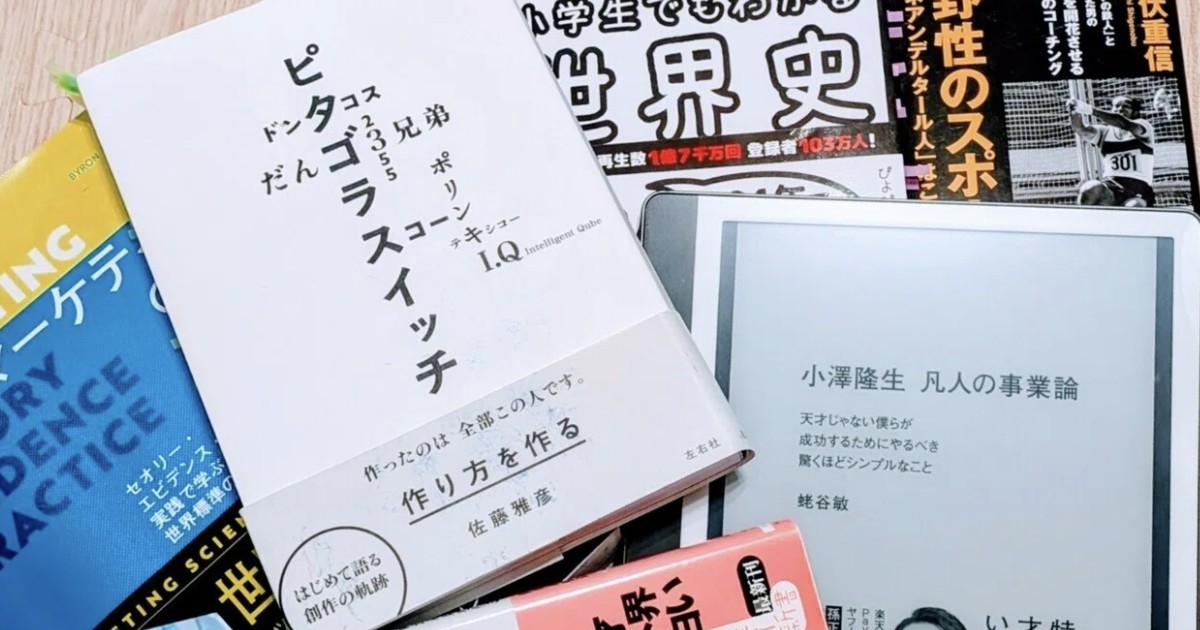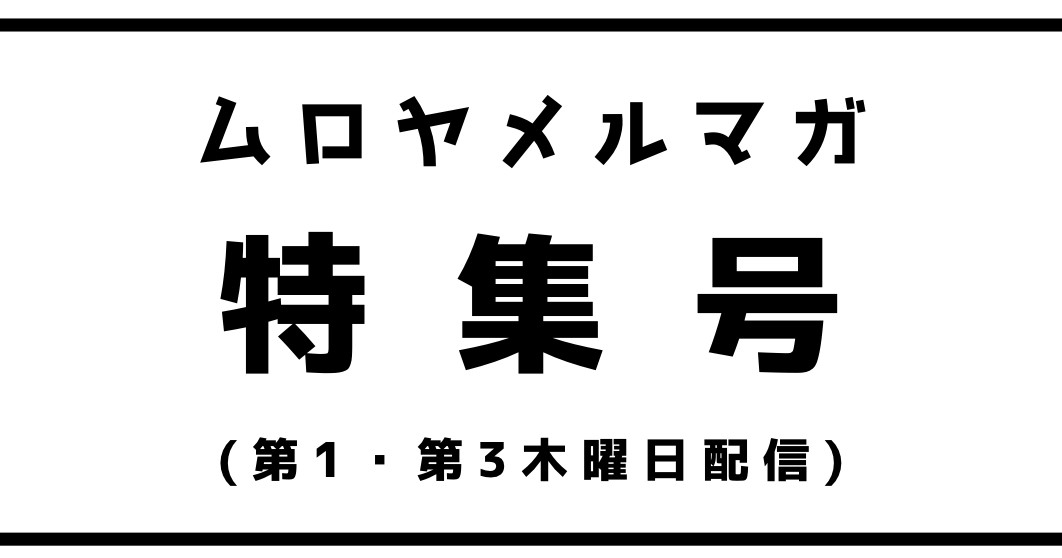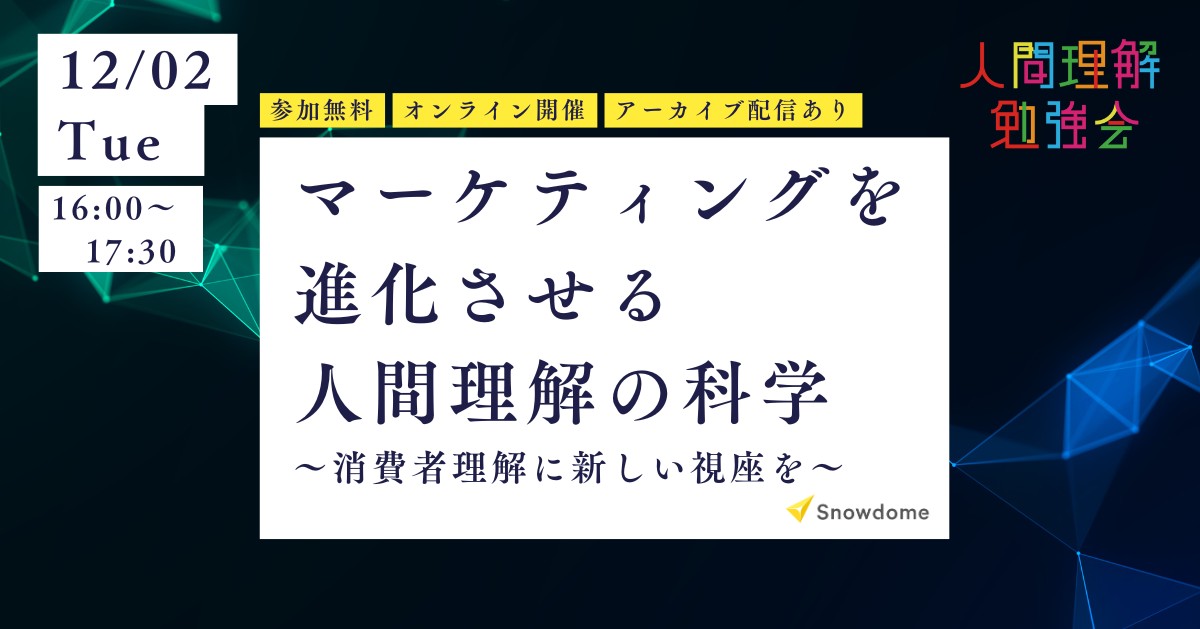超ファネル思考で俯瞰する
私は獲得型のWebマーケティングからブランディングなどの認知施策の領域に幅を広げていったのですが、獲得型の視点しか持たないまま仕事をしていると陥る罠があると感じました。
「ファネル」という言葉を耳にしたことがあると思います。
認知→興味・関心→比較・検討→購入→再購入と、商品やサービスを知ってから買うまでの流れについて、それぞれどの状態のお客さんが、どれくらいいるのかを考える際に役立つフレームワークです。
Webマーケでやれるのはファネルのごく一部
WebマーケターはGoogle AnalyticsやSearch Consoleなどのデジタルツールの数字に頼って業務を進めがちです。ファネルでいうと、なんらか興味・関心を持ってサイト訪問した段階です。
ここの数字は管理画面を提供しているGoogle等のプラットフォームが作った指標です。表示回数、クリック率、CPC、コンバージョン数など。
ここで与えられた数字からは、人間の姿は見えづらいのですよね。管理画面の指標は、アクションの総体の数字ですから。インプレッション323,434、クリック数142とかで。

いくらサイト流入を増やすために広告を打ったり、SEO対策をしていても、そもそもなぜお客様が自社商品を選んでいるのか「自社の強み」や、逆に離反されてしまう「弱み」を理解しないまま闇雲にWeb施策を続けても全体最適にはなりませんよね。
管理画面上で得られる数字だけで仕事を進めるのではなく、市場全体の状況やお客様から得られる生のデータも分析し、商品やサービス自体の価値を磨くことが全体戦略やブランディングを考える上で大切だと痛いほど学ばされました。
市場をもっと見ろ、顧客をもっと見ろ、アッパーファネルをもっと見ろと。
Webサイト訪問以降の領域だけでなく、顧客視点で全体像をイメージしファネルの各段階の解像度を高めることで、どこがボトルネックになっているのか特定が格段に行いやすくなる良さがあります。
そこで今回お裾分けしたいと思ったムロヤの自作フレームワークが「超ファネル思考」です。
俯瞰してみやすくなります。
図はこちら。

BtoBマーケを事例にご紹介します。
[1]マーケット全体に対する顧客の認識から購買状態までのファネル
言われてみれば当たり前すぎるのですが、獲得型のWebマーケティングどっぷりになると目が行かないのがアッパーファネル。トップオブファネル。要はサイト流入に至る前のファネルです。
リスティング広告で取れる認知量はたかが知れています。精度の高いターゲティング広告でimpを絞ることは、逆に言うと広く知らしめられないということの裏返しですから。
この領域を獲得型マーケどっぷりな人、つまり5年くらい前の自分を思い浮かべながら、どうやったら理解しやすくなるかと考えてみました。
まず、アッパーファネルのアッパー部分はなんだろうか。その指標について考える際に有効なのがTAMです。
そこから考えると、認知度とはターゲット市場のうちの何人が自社商品を認知しているのかだと繋げて理解できますし、何人が自社を選びたいと思っているのか(購入意向)、一度は商品を利用したものの今は利用していない人はどれくらいいるか(離反)等の指標から市場の状況は見えてきやすいとよく理解できます。
(西口さんの顧客起点マーケティングの本で紹介されていたこの調査メソッドはシンプルなのに得られる示唆が多いすごいメソッドだなと思いました。
-
このカテゴリーに関して知っているブランド名をお答えください
-
これまでに買った(使った)ことがあるかどうか
-
どのくらいの頻度で購買しているか(毎日、毎月、三ヶ月に一回、最近は買っていないなど) )
他にも、ブランドイメージ、戦略的ブランドエクイティの認知、 指名検索数とかも該当するでしょう。Webサイト訪問前(オウンドメディア接触前)のポテンシャルを覗きに行く感じです。あとは競合との競争状況とか。
詳しく学びたい方はこの辺の本とか、記事とかどうぞー。
なお、広報領域にどっぷりだけど幅を広げたいって場合は、下記のような下のファネルにも目を向けると良いかなと思います。例えば、PRとSEOの合わせ技とかありますし。認知とれてもCV取れないとか悲しいですし。
[2]WEB流入からCVまでのファネル(おもにデジマ部門が見る数字)
ここのファネルは獲得型人間にとっては得意領域かと思います。
例えばBtoBのリード獲得のファネルにおいては、
・インプレッション数→クリック率→サイト流入数、リタゲマーク数
・サービスページ訪問数→フォーム遷移率→CVR→CV数
という指標があると思います。
あるあるかと思いますが、いくら問い合わせ経由のリードの受注率がいいからと言って、魔法のように問い合わせ数は増えていきませんよね。問い合わせをしたってことはどこかで認知して、指名検索なりでサイト訪問して、そこから問い合わせフォームを通過いただいたわけです。
また、リード獲得においても、「毎月コンスタントにリードは取れるものの、いつも同じような客層だなぁ」と不満に思っていても、それはインプレッション数等のざっくりした数字だけを見ていて、どんな見込み客にリーチできているのかの視点がないメディアプランニングやコンテンツのオファーになっているからそのような構造に陥ってるだけかもしれません。
この超ファネル思考の使い所として、「[2]WEB流入からCVまでのファネル(おもにデジマ部門が見る数字)」のファネルで課題に感じる時、もしかしたら「[1]マーケット全体に対する顧客の認識から購買状態までのファネル」のファネルの改善が必要かもしれないと目を向けやすくなることです。上流工程からの見直しへ。
マクロの一枚絵にして脳内に焼き付けて覚えることで、視野狭窄を防げるのです。
[3]CVから成約までのファネル(おもに営業部門が見る数字)
そして、リード獲得後から成約までの流れでは、
アプローチ数→面談設定数(来店率)→商談化率→商談数→受注率→受注数
という指標があると思います。超ざっくりですがこの辺で。
[4]成約からLTVまでのファネル(おもにCRMやCSが見る数字)
成約後のLTV向上を目指すファネルについては、F2転換率や、RFM分析の「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の指標、継続率や解約率などがあるでしょう。ざっくりですがこの辺で。
(超ファネル思考のメインメッセージは「アッパーファネルにも目を向けよう」ですので。)
まとめ
Webマーケに従事する多くの人は、サイト流入からCVについては実際に業務でも関わりがあり、イメージしやすいと思います。しかしそれはファネルのごくごく一部。言い換えれば、お客様の生活やショッピング行動のごくごく一部です。
ブランディング領域もマスターしたいなど、もっと全体最適で設計したいなんて方がおりましたら、この「超ファネル思考」を参考に今の獲得型施策と認知施策を繋げて理解すると良いです。
俯瞰することで繋げて理解しやすくなりますから。
行き詰まった時にこの超ファネル思考の図を眺めると、「この辺がボトルネックかもな」「来期はこのファネルの箇所をテコ入れしよう」と発想しやすくなると思います。
他にもたくさん書いています。
メルアド登録いただくだけで読めますので、ぜひ登録してください!
すでに登録済みの方は こちら