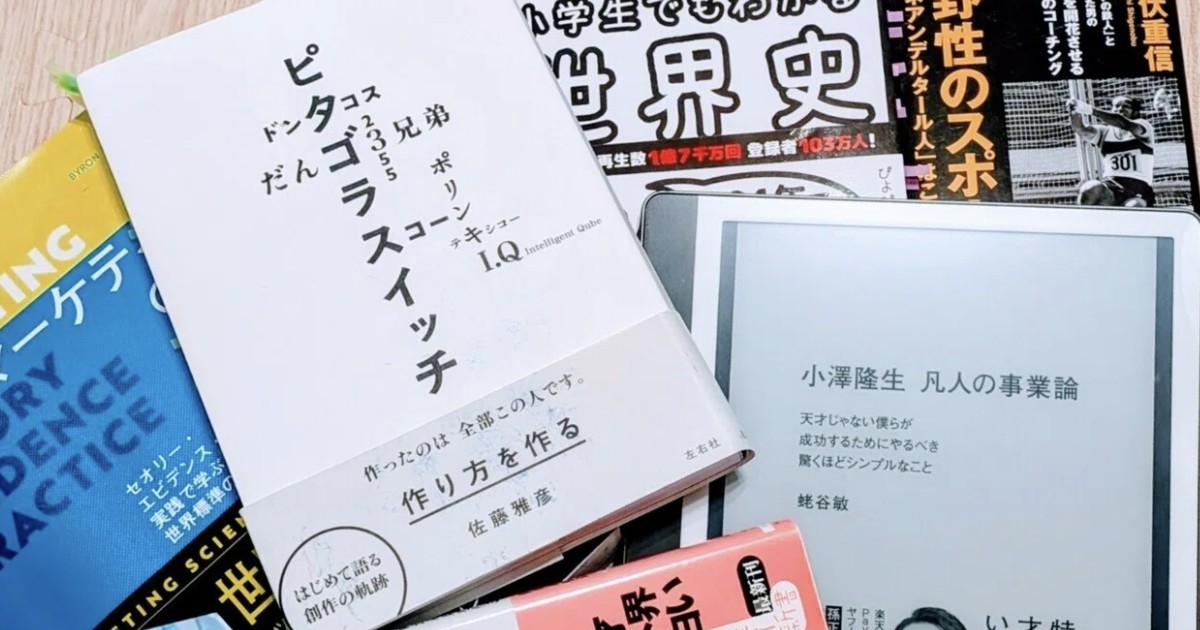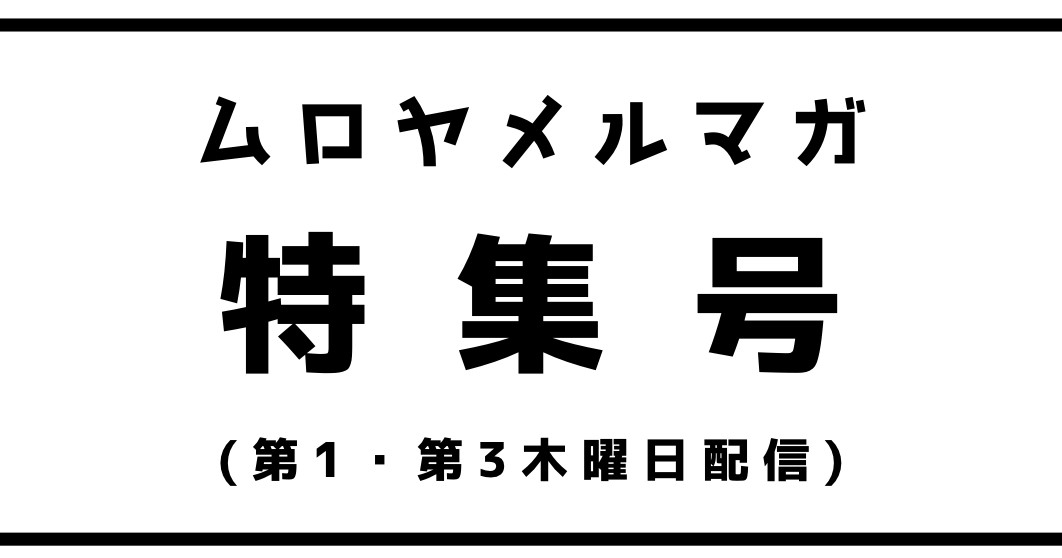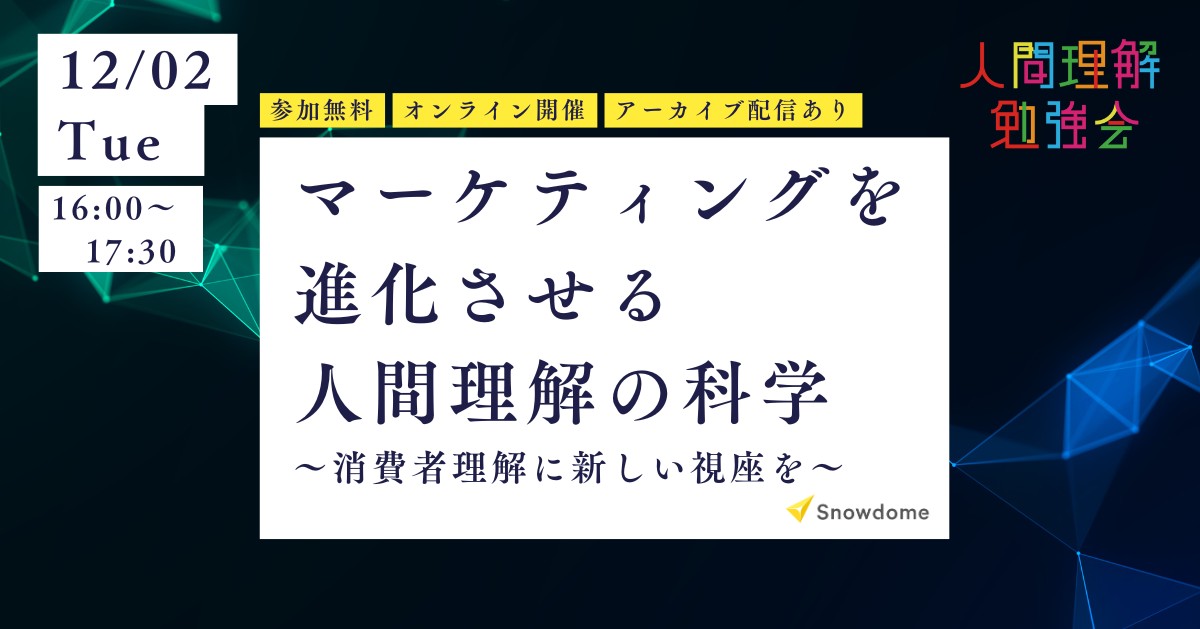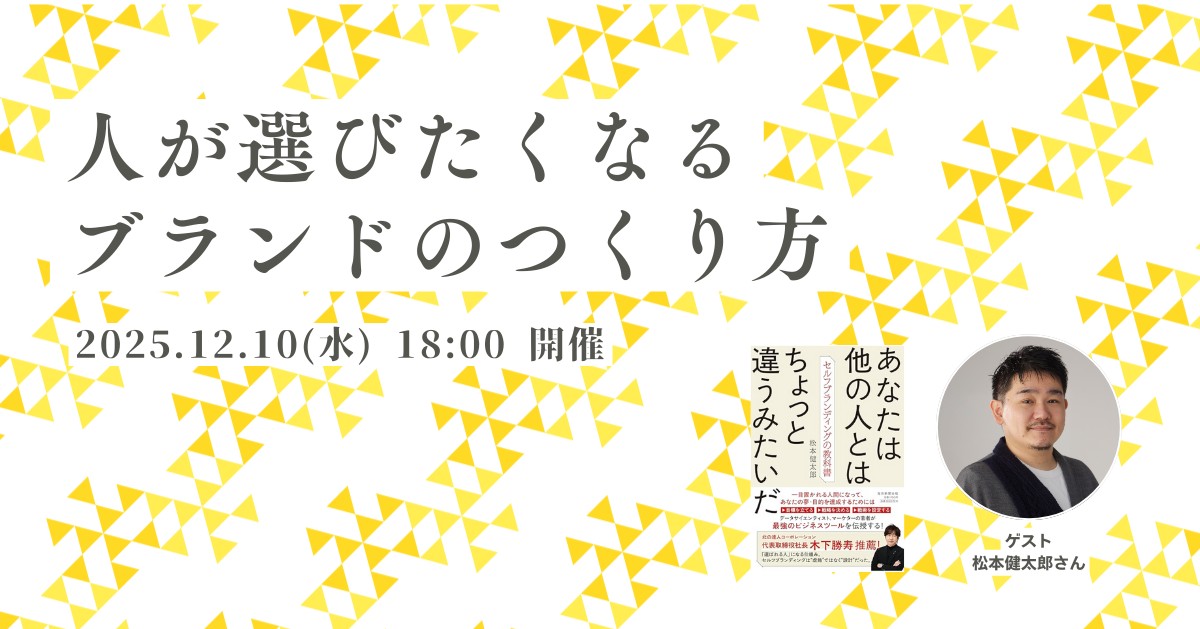人はなぜマーケティングの科学に惹かれるのか
こんにちは、スノードームの室谷です。
今回は、人はなぜマーケティングの科学に惹かれるのか、というテーマでお届けします。
人気ですよね、こういう本。
ところで、どうして人はこういう科学に惹かれるのだと思いますか?
エビデンス・ベースド・マーケティングのブームは、どういうインサイトをついているのでしょう?
まず、サイエンスなので大失敗が防げる、というのもあるでしょうねぇ。失敗回避です。
成功確率を高めるためにもサイエンスの世界でわかってることを取り入れるのは超重要ですよね。
ありがとう、先人の知見、という感じです。
ちなみに、もっと生々しい人間の心理として、こういう側面もあると思いませんか?
組織を動かすための御信託が欲しい!
自らの意思決定のための情報・知識という側面もあれば、自分が所属する組織を動かすために使いたいという側面もあると思います。
ベンチャーにいたりトップダウンでどんどん決められるような立場には全く共感されないかもしれませんが、大企業だとあらゆる部門からいろんなことを言われまくります。重箱の隅を突かれまくります。(重箱の隅を突く側も「うちの部署として言っておくべきことは言ったぞ!」とちゃんと仕事をしたんだぞと感じたいのです。)
「実行したいけどうるさい奴いるんだよね」という悩みを持つ方に、そんな中でも「これでいくんです!」と言えるものがあれば心強いですよね。抵抗勢力への武器が欲しいというニーズもあるのかもしれません。
ダブルジョパディ的にこうだから、メンタルアベイラビリティ的にこうだから、脳は省エネだから広告クリエイティブはこういう方向にしないと失敗する、メディアプランニングは増分リーチの観点でこうだから、市場浸透率を高めるためにはこのセグメントだから、、、などなど。
「これは私の意見ではなくデータの結論だ!」と語れます。代弁してくれるんです。
「それはあなたの意見でしょ」と反論されにくくなり、説得を助けてくれる材料になります。
横槍を減らしたいニーズは切実かと。抵抗勢力との交渉コストを一気に下げる御神託機能があるのでしょう。
そんな感じで、科学そのものは真理の探究で、基本的に「なぜこうなるのか」という問いに答えようとしますが、「科学的にこうだから」は人を動かす要素になります。
・科学的根拠で子育て
・科学的根拠で効率的な勉強
・科学的根拠で筋トレ
・科学的根拠で健康法
どれも魅力的に感じますよね。
科学と技術は別モノですが、科学にはこのような技術的側面があるなとふと思ったという話でした。
マーケティングは実行フェーズにおける組織の問題がめっちゃ大きい!
ここが解決されないことには、いくらいい戦略や施策アイデアがあっても動けません。
組織づくりに関しては、過去にnoteで書いてるのでこちらもご参考になれば幸いです。
マーケティングを最大限に機能させるためのチームづくりや、マネジメントにおける重要なポイントをまとめています。
『マーケティングの科学』の本がテーマのイベント開催!
この本をテーマにしたキーマケLabさん主催のイベントにてお話することなりました!
この本に関するミニ講演的な話や、キーマケLab 編集長の川手さん(@RKawtr)とのトークセッションなど予定されています。
2025年7月18日(金)の夜にご都合があう方はぜひ!(だいぶ埋まって残り5名ほどらしいです)
【オフラインイベント】『マーケティングの科学 セオリー・エビデンス・実践で学ぶ世界標準の技術』を肴にゆるトーク🍺 in 赤坂見附 7月18日(金)19:00~
弊社・スノードームのNotionには「『マーケティングの科学』『ブランディングの科学』のおさらい」という名のドキュメントをまとめておりまして、このイベントではそちらの内容をお裾分けしたり、日々の実務でどう活かされているかなどについてお話しようかなと思っております!
すでに登録済みの方は こちら