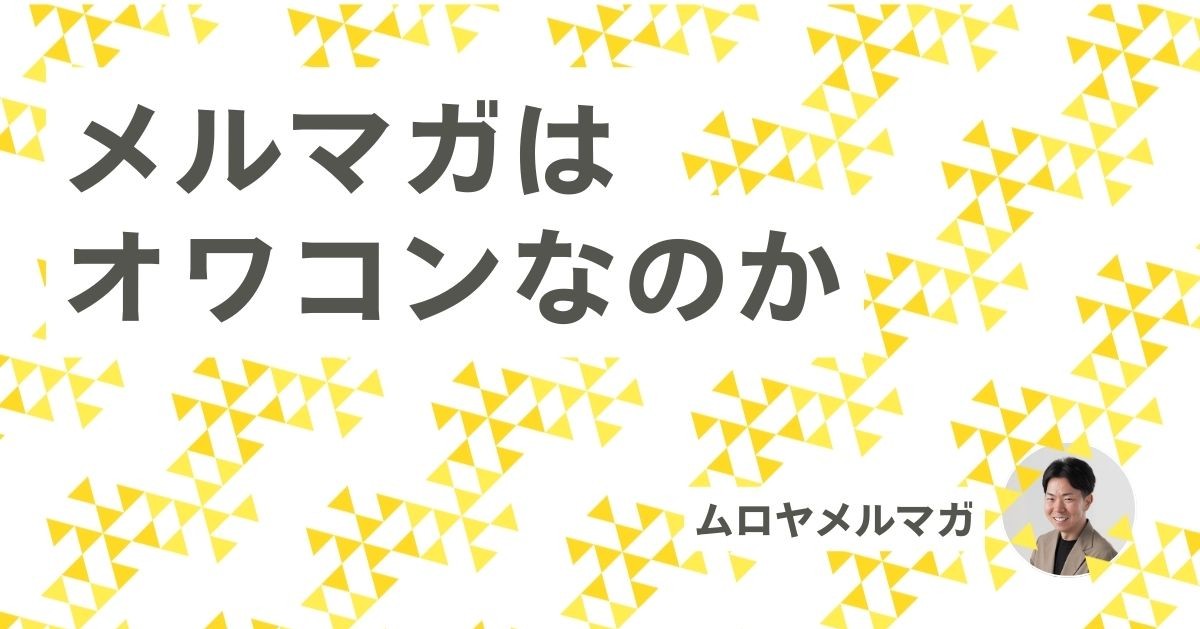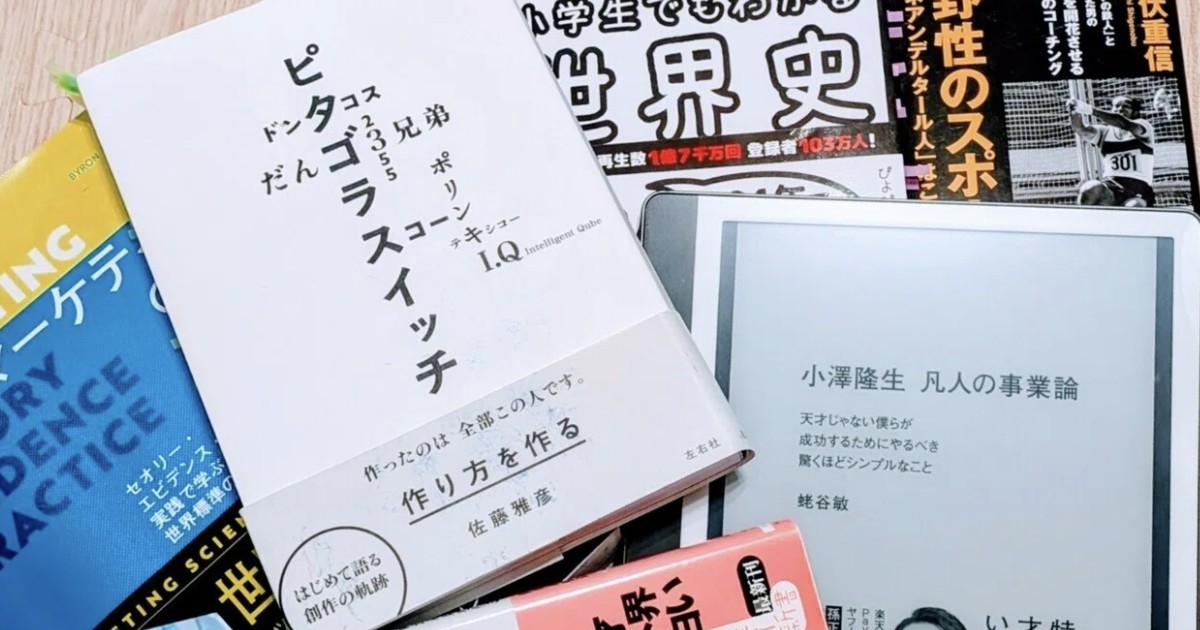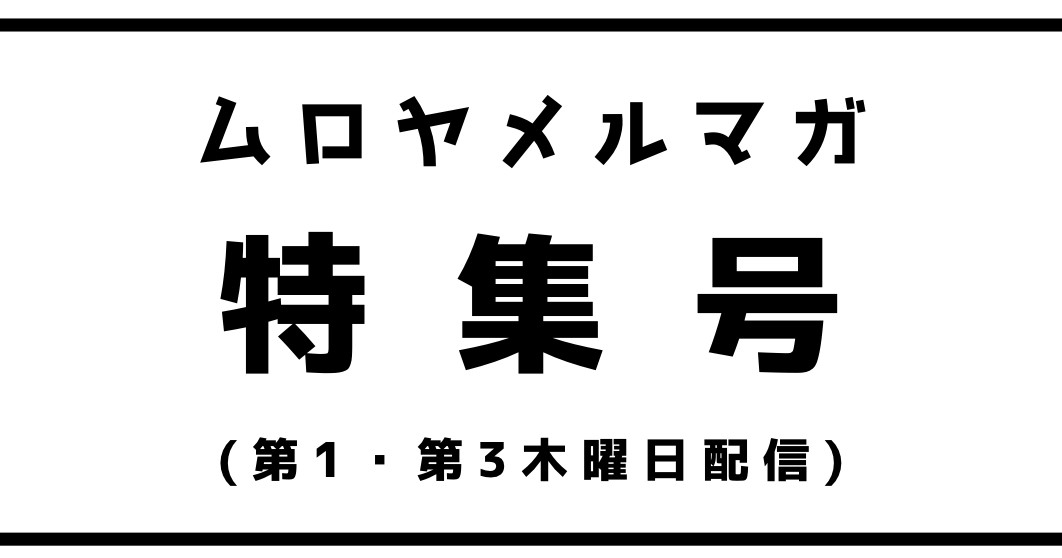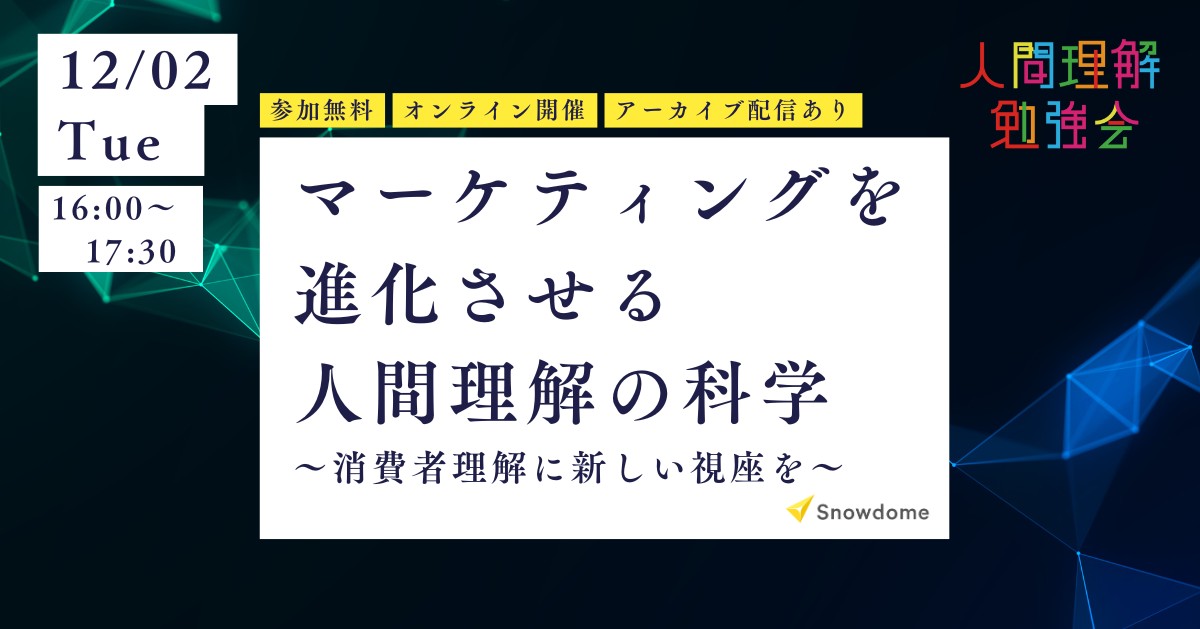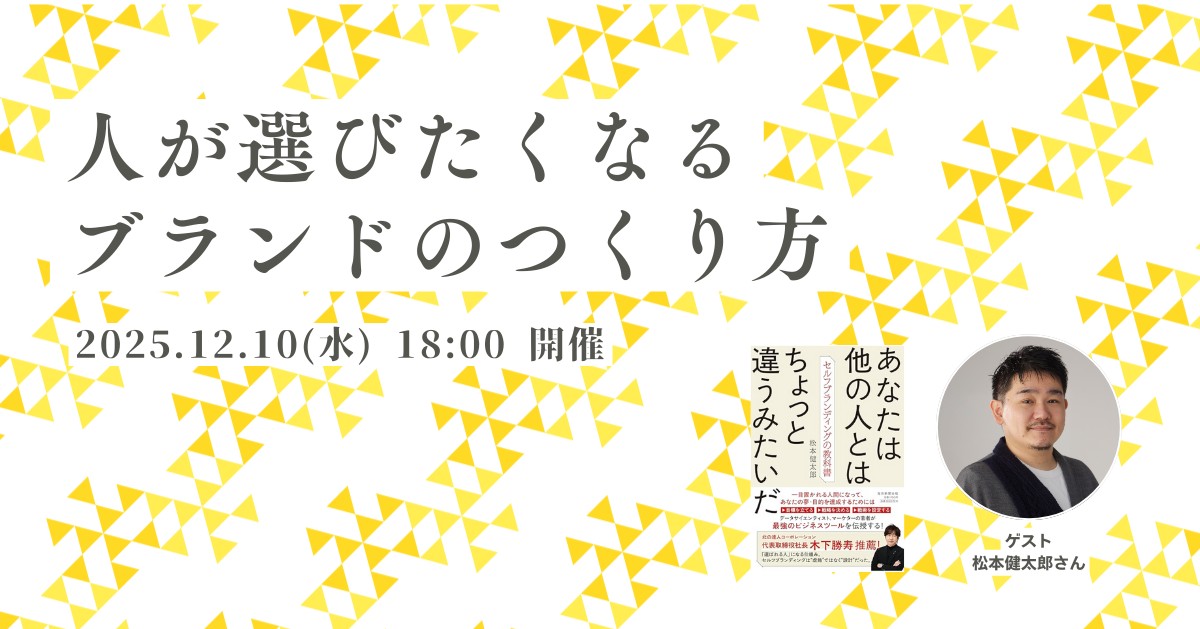読書感想文:「マーケティングの科学」を読みました
率直な感想
まず感じたのは、「教科書じゃん」ということ。
(多分ベースはこれ)バイロン・シャープ先生がいる南オーストラリア大学のマーケティングの教科書です。


(こちらも持ってる)
そして相変わらずフィリップ・コトラー氏のセグメンテーション・ターゲティング理論に対する批判に対する論調が非常に熱を帯びているという点です。バイロン・シャープ氏、たぶんこの章に一番魂込めてますよね。
また、一見、バイロン氏の新しいメソッドが書かれているのかと思いましたが、『(通称)ブランディングの科学1、2』や『ブランディングの科学 独自のブランド資産構築篇 / 原タイトル:BUILDING DISTINCTIVE BRAND ASSETS』を読まれていたならば、既知の内容が多いと感じると思います。(まぁ、帯に集大成とあるからそりゃそうか)
ですので、過去の本を読んだことがあるならば、それらの復習も兼ねて、広いマーケティングの世界を再確認しに行く、みたいな感じかと。教科書なんで。
あと、個人的に疑問に思った点としては、『(通称)ブランディングの科学2』をバイロン・シャープ氏と共著し、『ブランディングの科学 独自のブランド資産構築篇 / 原タイトル:BUILDING DISTINCTIVE BRAND ASSETS』の著者であるジェニー・ロマニウク先生の名前が見当たらなかったことです。
今回バイロン・シャープ氏が筆頭著者として名前を連ねているおり、著者紹介には20名以上の名前が挙がっているものの、その中にはいませんでした。
その点が気になりました。LinkedInを見る限り、辞めたわけではないようですが、この本を読んで一番気になるのは、むしろそうした内容でございます。
本書の構成
本書の構成は詳しくはAmazonをご参照いただくとして、こんな感じでした。
Chapter1「マーケターに求められる資質と業務」から始まり、続く第2章では消費者行動と顧客行動が扱われ、ロイヤリティや、人がブランドなどを忘れやすいという性質、カスタマージャーニーなどが論じられております。網羅的です。
このChaper1と2の内容から始まるのがいいなと思いました。いきなり抽象度の高い理論ではなく、職能とお客様を理解することから始まる。
また、小売業のフィジカルアベイラビリティ、プライシング、販売とセールスマネジメント、そしてマーティンコミュニケーション関連では第11章の広告、第12章のメディアプランニング、第13章のマーケティングプランの開発と実施あたりが実務でも重宝する箇所だと思います。
その他にも、第14章のグローバルマーケティング、第15章の倫理と社会的責任、第16章のソーシャルマーケティングなど、幅広い分野を学べる内容だと感じました。
詳細については、14,000円+税という躊躇する価格の本書を読んでいただければと思いますが、特に注目すべき箇所を簡単にご紹介します。
また、時間がない場合でも、各章末にまとめの箇条書きがあるんで、それから読むと良いでしょう。
「ブランディングの科学1、2」を読んだことがある人は、各章末のサマリーを見ることで、重要なポイントの復習、そして改めての学びの実行状況のチェックができるかと。
本書についていいなと思ったところ
本書についていいなと思ったところは、Chapter1「マーケターに求められる資質と業務」が明確に示されている点です。マーケターという職能の魅力を語るという点で非常に興味深く感じました。
また、イントロダクションでは、「特にマーケティング幹部は消費者の購買行動を理解できなければならない」と述べられており、これは言われてみれば当たり前ですが、こう言われてるということは当たり前に幹部全員ができてるわけではないということです。この理解がなければ、投資が無駄になるため、非常に重要な指摘ですよね。
あと私も「マーケティングの科学」をパラパラ読み返しながら、改めてマーケティングには様々なパターン・規則性や潮流が存在するため、それらを把握することが重要だなと改めて思いました。
全ての状況に適用できる経験則ではありませんが、概ねの傾向を把握することで、「この商品カテゴリに属してるってことは、こういう購買行動の傾向がありそうかな」と当たりをつけやすくなるからです。
チャプター2の消費者行動と顧客行動について。
「購買行動を理解することなくして、適切なマーケティングの意識決定を行うことはできない」と、まさにその通りだなって、強く頷きながら読みました。
あとこういう理解って、「やって終わり」の知識じゃないですからね。ストックの知識、ナレッジにもなります。
よって、組織として消費者理解や購買行動の理解を積み重ねられているか、学びが蓄積されているかは改めてこのGWに振り返ってみても良いのではないのでしょうか。インタビューやアンケート調査など。これら取り組みを強化していく意義を深く感じているかどうかは、成果を左右する大きな要素だと思います。
デジタルな現場であれば、GA4ばっかり見ないでアンケートだったりインタビューとかもどんどんやっていくのがいいと思います。
進化心理学についても触れてる
あとミニコラム的な感じで、「進化心理学で読み解く購買行動の4つの動機」というコーナーがありまして、ここが痺れます。本書の中でもサラッと語られてたんですが、個人的には超注目コーナー。
進化心理学によれば、大体その消費の多くの側面をを4つのダーウィン的同期の観点から説明することができると。まさにです。面白いです。
1、生存
2、繁殖
3、親族への投資
4、互恵性
「この施策、どの本能に触れてるんだっけ?」って問い直すだけで、訴求の軸がシャープになりますよ。人間理解、大事です。
地味だが大事、マーケティング指標
あと、様々なマーケティング指標に関する章があります。マーケ経験者なら全部知ってるわいって話ですが、地味に見えて、すごく大事なパートです。
財務的指標、行動指標といった多岐にわたる指標について整理されています。
特にデジタルマーケティングでは、インプレッション、CTR、コンバージョンといった管理画面上の数値だけを見ているケースがありますが、本書から認知指標を含めた多角的な視点が得られ、ハッとさせられるのではないでしょうか。
宣伝:スノードームの「超ファネル思考」もご参考になると思います。俯瞰的に捉えられる視点を持つことに役立ちます。
超ファネル思考
ここが本丸か「セグメンテーションとターゲティング」
あとはやっぱ辛口なのがチャプター6の「セグメンテーションとターゲティング」です。
ここはバイロンシャープ先生もこの章の著者に名前入ってますからね。めちゃめちゃ気合で書いたと思います。
イントロダクションから刺激ですし、ここだけ世界が違いますw
「(中略)本章では、これらの思い込みを深く考察して、その誤りを指摘する」という入りです。どんだけ攻撃的なイントロダクションなんだと、そういうふうに私は感じ取ったわけでございますw 刺激的なんで読んでおいてください。
「ターゲットは絞れば絞るほど正しい」みたいな安心感にハマったことは誰しもあると思います。あるあるですよね。「ピンポイントに響く施策=精度高い」って思いたい。でも、それって認知もリーチも狭いということの裏返しですから。
現実的には、より多くの方々に広く届けられるならそっちのほうがいいに越したことはないですよね。価値提案についても1/100に響くよりも、50/100くらい様々な方々に広く響くほうがいいですよね。普遍的に喜んでいただけるような価値提案です。
なるべく多くの人に喜んでもらえる施策に良いに越したことはないのです。不用意に狭めるなよと。
多くに共通するインサイト発掘が重要な理由がこれです。だから人間の根源・原理・仕組みを知ることは大切。個々の小さな違いよりも、根源的な深い共通点に着目する方がマーケ戦術をしましょう。
このようなことが学べる人間理解勉強会もぼちぼち再開します。
BtoBマーケは?
あと、各章の終わりあたりに「BtoBマーケティングの応用」に関するミニコラムがございます。ちゃんと章ごとに触れてくれてるのはありがたいのですが、これはBtoBマーケティング従事者からすると激しく物足りない印象を受けるなぁと思いました。
よくあるマーケティング系の他の本でもBtoCをメインに解説しつつ「BtoBも大体同じである」みたいに一行で済ませちゃうほんもありますし。「大体同じと言われても、ディテールのところで差異があるから現場の方が困っているんだよ!」という現場からの声が私には聞こえてきます。
その後は広告やメディアプランニングに関する章があり、ここは広範な視野で捉えるっていう感じの内容です。この部分は、実際の業務においては、より詳細な実用書を見たほうがいいですが、初学者にはこういう世界が存在するのだ伝えられる本だと思いました。
そんな感じの教科書でした。
参考:関連記事として2020年に書いてたnoteを掘り出しました
神本こと『ブランディングの科学』と『Building Distinctive Brand Assets』について読んだ感想
定期的にマーケティングに関するニュースレターをお届けします。ぜひ無料登録してください。
すでに登録済みの方は こちら