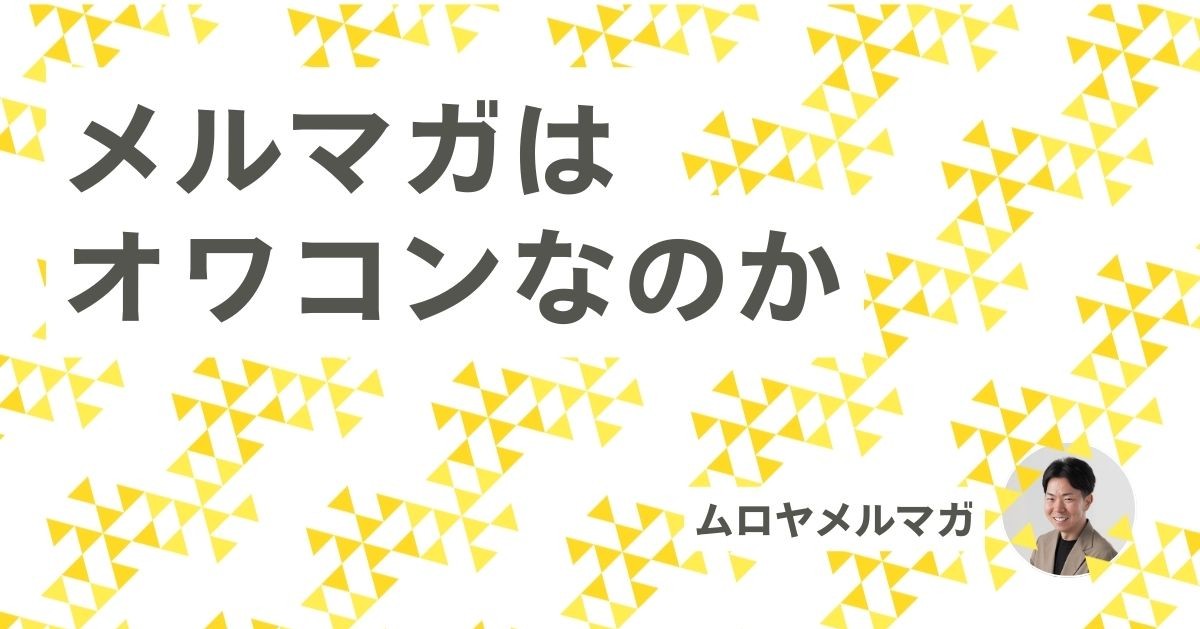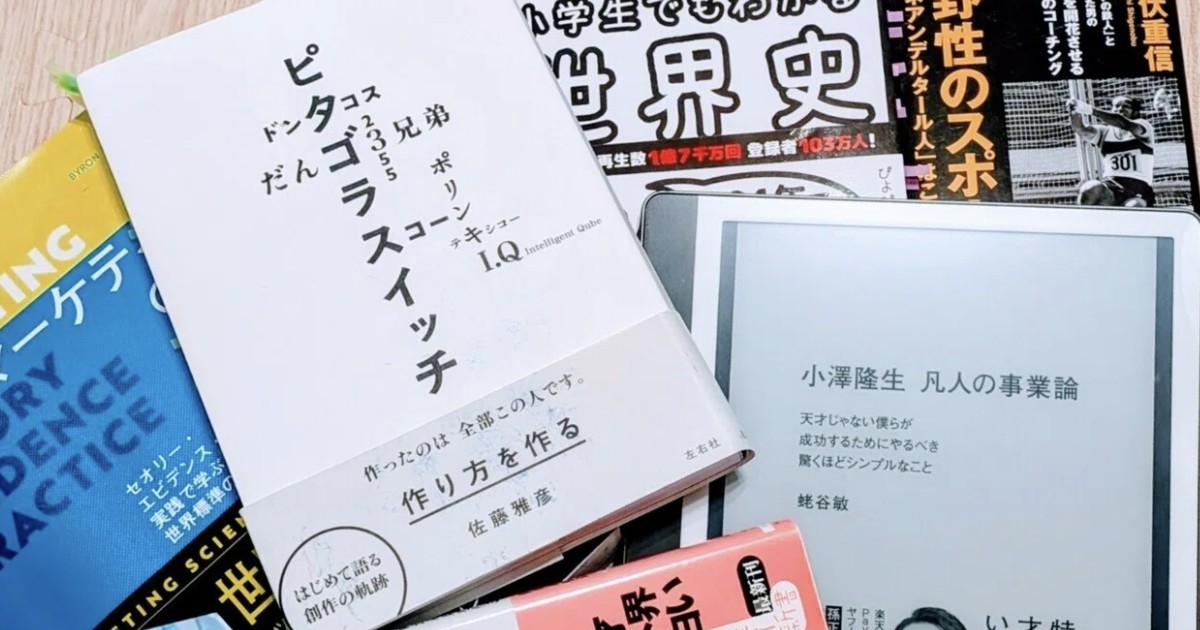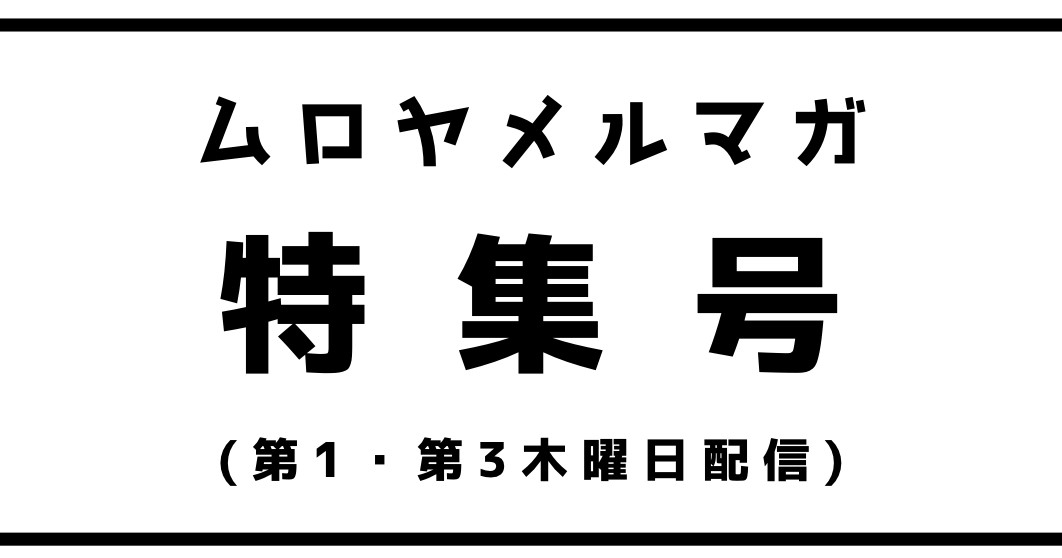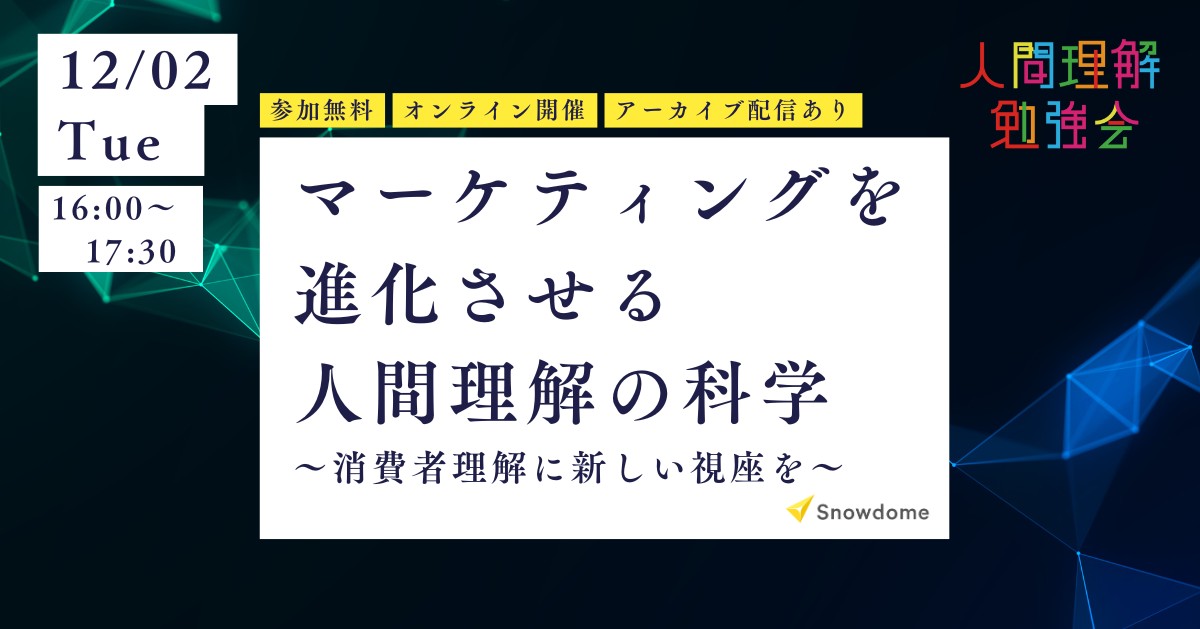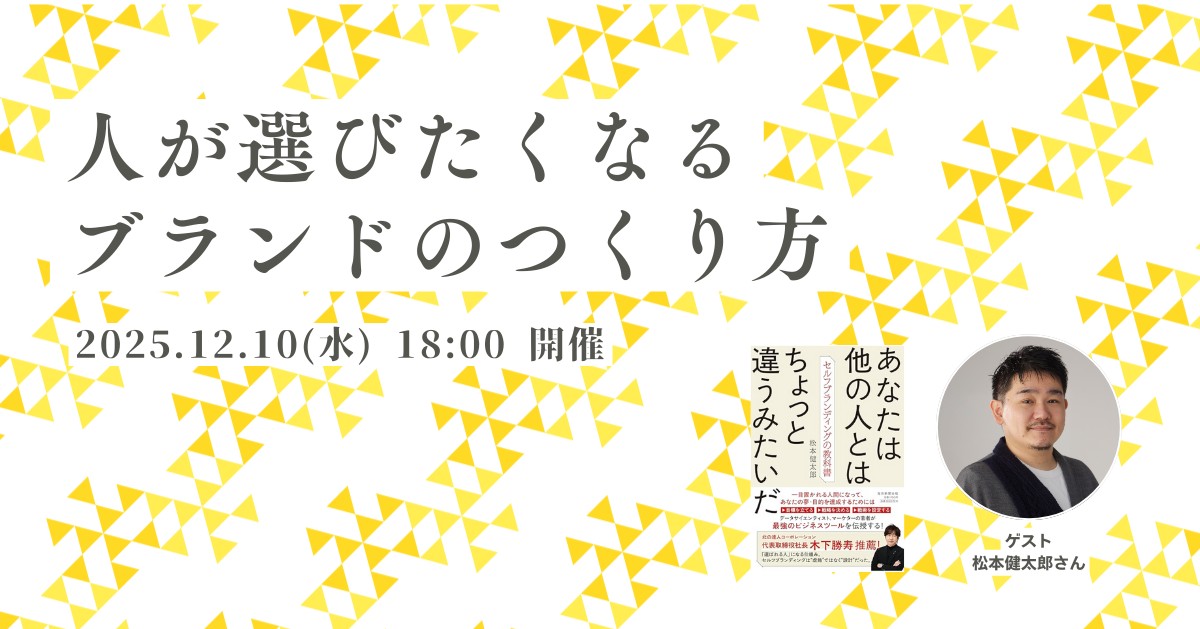生成AI時代の競争優位なコンテンツ
デジタルコンテンツはコピーが容易。工夫なしなら競争優位性はゼロ。すぐに真似されて、速攻で追随されます。生成AIの登場で尚更そう思います。
競争優位なコンテンツってどういうものだろう
・真似されないコンテンツ
独自の強みやアセットに立脚したコンテンツを出す(ここの専門性はピカイチとか、動画とかこのコンテンツフォーマットなら強いとか)、俊敏にタイムリーにコンテンツを出せるスピード体制とか(上長の長い承認リレーがいらない権限移譲とか各所の連携とか。作りたいなと思ったコンテンツのアイキャッチを素早く作れて供給されるようなチーム体制も強みになる)
・(競合が)されたら嫌なコンテンツ
競争相手が立場的に言えないことを言う、不都合な真実を言う、競合ではできないくらい自社ではリソースを徹底的に投下する、内部の分断を煽る(これは本当に嫌だw)とか
・どこよりもはやくフレッシュなコンテンツを出す
競合が同じことをやっても、先頭を切った人とか同じ印象は得られないから。二番煎じになりますからね。一等賞の価値。
とかありそうですよね。
そして、「コンテンツ単体へのアプローチ」と「コンテンツとプラスアルファの複合要素でのアプローチ」にも分けられるなと思いました。
①コンテンツ単体へのアプローチ
こんな方法もあると思います。
・コンテンツを定期更新する
まぁリライトですね。コピーされて終わりにならないように、そのコンテンツを磨き続けること。そうすれば過去時点にコピーされたものは劣化したということになるから。こちらに磨きがかかれば同列になりませんからね。また、常に新しい情報やエンターテイメントを提供することで、読者や視聴者の関心を引き続けることができるメリットもあると思います。
・コンテンツを定期更新してそこへのアクセス権を販売する(買い切りではなくサブスクへ)
上記をもっとパワーアップさせて、アクセス権を販売する形式のサブスクリプションモデルを採用することも考えてください。読者や視聴者は定期的なコンテンツの提供に対して有料でアクセス権を購入し、継続的に価値を享受することができます。
・コンテンツに造語や実体験、自分自身だからこそ言える物語を組み込む
他にはない魅力や新しさを提供しましょう。EEAT的な観点からも言えますね。造語は一次情報になり、引用とか被リンク施策にも活かしやすい。このまんまコピーできない状態になりますからね。商標の侵害とか、「あなたにはそれは言えなくない?」って状態になりますから。こういうコンテンツへのオリジナリティ追求の過程で、コピーされにくくなります。
②コンテンツとプラスアルファの複合要素でのアプローチ
単体のコンテンツに加えて、プラスアルファの要素を組み合わせることで競争優位性を高めることができます。